- 『フェルマーの料理』の登場キャラと声優陣の一覧と配役
- 声優ごとの演技の特徴やシーンごとの“声の演出”の見どころ
- 声優の表現によって物語に生まれる“感情の深み”や魅力
数学と料理という、一見遠く思える2つの世界を“エモでドリフト”させるアニメ『フェルマーの料理』。その魅力を形作る大黒柱は、キャラクターたちを震わせ、画面の奥まで“感じさせる”声優陣です。
本記事では、天才数学少年・北田岳と、一ツ星シェフ・朝倉海をはじめ、ヴェルス学園やレストラン「K」の個性豊かな面々まで。「顔が見えないからこそ感情が込められる」――そんな“声の物語”を紡ぐ声優たちを、あなたといっしょに鑑賞します。
読み終えたころには、推しキャラの声に耳を澄ませるたび、心の皿がじゅわじゅわ染まっていく、そんな感動を。
“数学少年”北田岳と“狂気のシェフ”朝倉海――主人公2人の声の温度感
『フェルマーの料理』のエモエンジンを回しているのは、間違いなく北田岳と朝倉海という2人の主人公です。
数字にしか心を許さなかった天才高校生と、食で人を掌握するカリスマシェフ。この2人のぶつかり合いと交錯を、声の力で“リアル”に変換しているのが富田涼介さんと坂泰斗さんです。
「感情の軸」が揺れるシーンほど、彼らの声は熱を帯び、画面越しに心をノックしてきます。
北田岳役|富田涼介──“計算式レシピ”を届ける声の透明感
北田岳を演じるのは、若手ながらも芯の通った演技に定評のある富田涼介さん。
彼の声が持つ澄んだ音色と理知的なテンポは、まさに“数学が主語”だった岳の孤高さをそのまま写しています。
特に第1話、初めて料理に興味を持ったときの「料理って、数式みたいだな……」というモノローグ。
そのセリフには「心を奪われる」というより「心が勝手に連れていかれる」ような、静かな衝撃がありました。
無機質だった彼の声が、話数を追うごとに少しずつ人間らしく、熱を持っていく──。
それはまさに“感情が開かれていく過程”そのものなんです。
朝倉海役|坂泰斗──“熱”と“狂気”をツインドライブさせる声の強度
一方の朝倉海を演じるのは、実力派声優・坂泰斗さん。
“狂気の料理人”と称されるだけあって、彼の声は柔らかさと狂気、理性と激情が混在する、非常に緻密な設計がなされています。
特に印象的なのが、第2話の名セリフ──「君の才能を、俺の厨房に預けてみないか?」。
低音で語りかけながらも、どこか理性を振り切ったような熱量がこもっていて、まさに“誘いの声”でした。
坂さんの演技は「ただの天才シェフ」ではなく、「美を追い求める狂人」でもあり、「人を育てたい孤独な大人」でもある、海の多面性を炙り出します。
その声を聴いていると、海という人物の“正気と狂気の狭間”が、まるでこちら側まで滲んでくるよう。
この2人の声の相互作用こそが、『フェルマーの料理』という物語に“体温”を与えている。
数式では測れない感情の変化、レシピにはない感動の余韻。
それらが、声という“目に見えない演出”で、しっかりと形になっているのです。
レストラン「K」を彩る面々――個性派キャストの魅力
「料理は、戦場だ。」
そんなテーマを地で行くのが、朝倉海が率いるレストラン「K」。
この場所は、ただ料理を出すだけの空間じゃありません。
人間の熱と、挫折と、矛盾と、プライドと──感情が鍋の中でごちゃ混ぜになって、やがて“何か”になる場所です。
そんな“心の厨房”を支えているのが、布袋勝也・ウィヴィア・赤松蘭菜・福田寧々・乾孫六といった、強烈な個性を放つ料理人たち。
その声に注目してみると、ただのサブキャラなんかじゃない、ひとりひとりが“主役級の温度”を持っていることに気づかされます。
布袋勝也(遠藤大智)|“強面スーシェフ”、声に乗る揺れと重み
第一印象は「こわ」。
黒髪オールバック+無精ひげ+ぶっきらぼうという、スーシェフ・布袋勝也。
ですが、彼の声を担当する遠藤大智さんの演技が絶妙で、ただの「怖い人」では終わらせません。
言葉少ななセリフの“音の置き方”が巧みで、ぶっきらぼうな中にも人間味と葛藤がにじみ出る。
特に、第3話での「……俺は、あんたが本気で料理してるのを見てみたい」には、彼なりの“信頼”と“期待”が、セリフの間(ま)からこぼれ出ていました。
ウィヴィア・ミロ/赤松蘭菜(永塚拓馬/依田菜津)|ペイントとレシピと少女の“揺らぎ”
次に、感性のペイント料理人・ウィヴィア(CV:永塚拓馬)と、真面目で繊細な赤松蘭菜(CV:依田菜津)。
2人とも“感情で料理をする”タイプですが、声のベクトルはまるで違います。
永塚さんのウィヴィアは、ちょっと浮世離れしたリズム感と優しさが同居していて、癖になる声。
対して、依田さんの赤松は、感情をぐっと抑えながらも、思いが声ににじむ“我慢の震え”が聴きどころです。
例えば「私、もっと上手くなりたいんです」──その一言だけで、彼女の過去、努力、焦り、全部が染み込んでくる。
福田寧々・乾孫六(池澤春菜/橘龍丸)|“ケータリングチームK”の温度感を支える声の表情
ケータリング側の寧々さん(池澤春菜)と、乾(橘龍丸)も忘れちゃいけない。
作品全体のテンションを調整する“声のバランサー”とも言える存在です。
池澤さんは、いつもの柔らかいトーンに“おせっかい感”を乗せてくる天才。
橘さんは、怒っても笑っても“筋が通ってる人”に聴こえる、低音の信頼感がすごい。
この2人の声が厨房やイベントを“わちゃわちゃ”させつつ、ちゃんと視聴者の心を落ち着けてくれるのは、演技の空気調整力あってこそ。
“料理アニメ”と一言でまとめるには惜しいくらい、このレストラン「K」は人間の匂いでいっぱいです。
そして、その“匂い”を、画面の外まで運んできてくれるのが声優陣の演技。
「声だけでここまで想像させるって、もう料理じゃん」──そう感じたら、あなたももう『フェルマーの料理』の沼に半分浸かってます。
数学と学園世界のキャスト群像――数理と青春の声たち
レストラン「K」の熱に触れた北田岳は、次に「学ぶ」フェーズへと足を踏み入れます。
舞台はヴェルス学園。そこは、未来の料理界を担う若者たちが、己の技と情熱をぶつけ合うアリーナ。
でも、ただ技術を磨くだけじゃない。
“過去との和解”や“仲間との衝突”、そして“夢の正体”を探し続ける青春の揺らぎが、この学園には満ちています。
その揺らぎを支えるのが、広瀬一太郎・武蔵神楽・魚見亜由ら、個性豊かな学生たち。
一見モブにも見える彼らが、ふとした瞬間に心を震わせる──それは“声の演出”が想像力を拡張してくれているからに他なりません。
広瀬一太郎・武蔵神楽(古川慎/若山詩音)|オリンピック競争を覗く声の“静かな熱”
まず、全国の数学オリンピック組もざわついたであろうキャラクター、広瀬一太郎(CV:古川慎)。
彼のセリフは常に“冷静”、だがその中にある“計算された熱”がすごい。
古川さんの声の真骨頂は、無駄のない抑揚の中に燃える意志を秘めること。
たとえば、「君のやり方じゃ、まだ甘いよ」といったセリフが、ただの忠告じゃなくて“評価とライバル視”の入り混じった混沌に聴こえてくる。
それは、声が“行間”を読ませてくれる演技だからなんです。
そして武蔵神楽(CV:若山詩音)。
彼女は“料理界の銀メダリスト”とも言える存在で、言葉少なく、でも存在感は圧倒的。
若山さんの声が持つ、やや冷たいけど澄んだ空気感──それが、武蔵の「プロフェッショナルとしての矜持」を滲ませます。
彼女の「料理に、情は要らない」というセリフ、震えましたよね。
あの声の冷たさが、むしろ“内にある激情”を想像させてくれるんです。
魚見亜由(永瀬アンナ)|スポーティな色気と“推し声”を重ねて
そして、ヴェルス学園の中でも一際“陽”のエネルギーを放つのが、魚見亜由(CV:永瀬アンナ)。
ポニーテールの快活系女子でありながら、時折見せる“不安定な目線”や“笑顔の揺らぎ”が、妙に心に引っかかります。
永瀬さんの声の魅力は、明るさの中に垣間見える“感情のグラデーション”。
声を張ったときのパワーと、ふと語尾が沈む瞬間の繊細さ──。
その緩急にこそ、“青春という波”に乗って生きる亜由の今が詰まっていると感じます。
特に、「私だって、本気で料理してる!」と声を張ったシーン。
あの瞬間、彼女が“ライバル”から“共感できる仲間”へと変わった気がしました。
“数理的正解”では片づかない、青春の矛盾や揺れ。
それを“声”という媒体で翻訳してくれるのが、これらのキャスト陣なんです。
セリフの裏にある葛藤、声色の中に宿る願い──。
このアニメの「学園パート」は、まるで声優たちの“青春再現ゲーム”を観ているような、胸のざわめきがある。
エピソードキャストの彩り加減――背景を支える声の演出
『フェルマーの料理』の魅力は、主人公やレギュラーだけでは完結しません。
むしろ1話ごとのエピソードに登場する“脇役たち”が、毎回物語の深度を引き上げてくるのです。
彼らは料理人でも、学生でも、家族でもいい。でも必ず「声に物語が宿っている」。
この章では、スポットライトの隙間で燃えている“背景の炎”に、耳をすませてみましょう。
各話ゲストたち|北田父や理事長、議員役などの“雰囲気造形力”
まず外せないのが、北田岳の父親役。
彼の声には、「正しさ」という圧力が染み込んでいました。
料理ではなく数学を選んでほしかった、という一種の“支配的な愛情”を、ただ説教くさくなく、理知的で冷たい声で演じていたのが逆に刺さる。
無言の間(ま)すら、責められているように感じる──まさに“空気で叱るタイプの親”を再現した名演でした。
一方、学園の理事長や審査員、グルメ評論家、スポンサーの政治家など、“権力側”に立つキャラクターたちは、どれも“上から目線”の声の設計が秀逸。
高圧的ではあるけれど、強すぎず抑揚でコントロールされた声──それは「支配する側の余裕」を感じさせます。
セリフひとつで「こいつ、裏で何枚も札持ってるな」と感じさせるのは、演技力というより“人間描写力”の高さですね。
子供・学生たち(海弓シュリほか)|モブからセリフに宿す“存在感”
そして忘れてはならないのが、子どもや若手学生たちの声。
特に、北田岳の幼少期を演じた海弓シュリさん。
彼女の演技は、“演技してない感”が最大の武器でした。
「天才だけど孤独」という感情を、過剰に説明せず、それでもちゃんと“伝えてくる”。
例えば、幼い岳がノートに数式をびっしり書いているシーンの独り言。
その声は、楽しそうなんだけど、どこか寂しそうで、でもどこか誇らしげで──
……感情が多層構造になってる。
その他の学生たちも、いわゆる“背景モブ”で終わらせない。
セリフ1つ、声のトーン1つに、ちゃんと「この子の物語がこの一言の前にある」と思わせる設計があります。
それが『フェルマーの料理』の“声の厚み”であり、世界観のリアリティを保つ声優陣の連携なのです。
声優って、主役じゃなくても画面の“奥”を深くしてくれる。
むしろ、画面の外側を「感じさせる」力こそが、プロの証明。
『フェルマーの料理』は、そんな声優の“裏仕事”まで含めて、五感で楽しめるアニメです。
感情翻訳の鍵を握る声優たち――“語りたくなる感動”を支える技術
アニメを観ていて、「あ、このセリフ、刺さる……」と無意識にスクショボタンに指が伸びる瞬間ってありますよね?
『フェルマーの料理』には、そんな瞬間が何度も訪れます。
そしてその刺さり方は、文字だけでは説明がつかない。
言葉の背後にある“感情の設計図”を読み解き、声という形に翻訳してくれる人がいるからこそ、心に突き刺さるのです。
それが、この作品に命を吹き込んでいる声優たち。
彼らの演技は「感情の可視化」であり、同時に「視聴者の感情と同期させる装置」でもあります。
声の“間”と“熱”、そして“余白”の設計
“演技”というと、つい大きな声・激しい感情表現を思い浮かべがちですが、実は逆。
本作のキャストたちは、むしろ「間(ま)をどう置くか」「どこまで言葉を詰めないか」で魅せてきます。
例えば、北田岳が料理に「正解がない」と気づき、言葉を詰まらせるシーン。
そこでほんの一拍、息をのむ「空白」が生まれる。
その空白に、観ている僕らの想像と感情が“流れ込む”んです。
まるで、セリフの続きを“自分の中で埋めてしまう”ような錯覚。
この余白の演技こそが、刺さるアニメの真髄です。
また、同じセリフでも、「怒り7割・哀しみ3割」にするのか、「戸惑い5割・決意5割」にするのかで、届けられる感情がまるで違う。
声優たちは、その“調合比率”を意図的に操作してるんです。
それってもう、料理じゃん。
過去作から拾う“演技の奥行き”──声優たちの役割が今に光る瞬間
もうひとつ、『フェルマーの料理』を観ていて何度も感じたのは、「この声、どこかで聴いたことがある」という既視感のようなもの。
それはつまり、過去作で積み重ねた演技の記憶が、いまのキャラに奥行きを与えているということ。
たとえば、朝倉海役の坂泰斗さん。
彼のこれまでの代表作には、理性的でいて感情的、強さの裏に脆さを抱えるキャラが多かった。
その“演技の歴史”が、朝倉の「料理の鬼」の中に時折見せる“人間らしさ”として浮かび上がるんです。
また、赤松蘭菜役の依田菜津さんも、内にこもるキャラを演じる名手。
彼女が声を乗せるだけで、言葉の裏側にある“不安”や“ためらい”がクリアになる。
「このセリフ、こんなにも静かに突き刺さるんだ…」って気づいたとき、
僕らは、彼女の“感情翻訳”に完全に導かれているんです。
アニメの感動って、作画や脚本だけじゃ成立しない。
それを“感情の言語”にしてくれる声優たちの技術こそが、作品を刺さるものにする。
だから僕はいつも言います。
「感動を抱えきれないときは、まず“声”を思い出せ」って。
『フェルマーの料理』声優一覧から見える“声の沼”まとめ
“数学と料理”、このありえない組み合わせを成立させたのは、ロジックやレシピだけじゃない。
感情を翻訳する声の演技──つまり、声優たちの存在です。
彼らの演技がなければ、岳の成長も、海の狂気も、レストラン「K」の熱量も、ヴェルス学園の青春も、ここまで“体感できる物語”にはならなかった。
ただ観るだけの物語から、“感じる”物語へ。
その進化を、僕らはまさに声を通して経験しているんです。
数学的思考も美味しい料理も、“声”を通せばもっと震える
数式は正解が一つだけ。
料理は正解が無数にある。
この対照的な世界観がぶつかりあう中で、キャラクターたちはいつも“正解じゃない感情”を抱えて葛藤します。
迷って、悩んで、でも進んでいく──そのすべての瞬間を、声優たちは「声」で支えている。
だから僕たちは、このアニメを観るとき、ただ耳で聴いてるんじゃない。
“感情のテクスチャ”を耳でなぞってるんです。
その感覚が、この作品をただの料理アニメじゃなく、「人生の縮図」として感じさせてくれる所以なんだと思います。
“推せる声のキャラ”への切符を手に入れるために
この記事をここまで読んでくれたあなたは、もう立派な“声の感度高め勢”です。
『フェルマーの料理』に登場するキャラは、どれも一度耳に焼きついたら忘れられない“声の温度”を持ってます。
でもそれは、ただ「上手いから」だけじゃない。
感情の裏側を丁寧に翻訳してくれてるからこそ、刺さるんです。
それが「推し声優」の原体験になるかもしれないし、「この声の人、他の作品でも聴きたいな」っていう新しい沼への入り口になるかもしれない。
つまり、『フェルマーの料理』は“声の沼の入り口”としても、めちゃくちゃ優秀な作品なんです。
さあ、次にあなたが『フェルマーの料理』を観るとき。
画面の奥から聞こえる“息の温度”や“言葉の湿度”にも、ちょっとだけ耳を澄ませてみてください。
きっとそこには、「もう一つの物語」が流れています。
語らずにいられない感情、それが名作。
そして、それを運んできてくれるのは、いつだって──声、なのです。
- 北田岳・朝倉海など主要キャラの声優が判明
- 各声優の演技がキャラの感情表現を強化
- レストラン「K」メンバーの人間味あふれる声の演出
- ヴェルス学園キャラの青春感を声で表現
- エピソードごとのゲスト声優も高演技力が光る
- “声の間”や“余白”が感動の鍵を握る
- 声優の過去作とのつながりも見どころ
- アニメ全体を“声”が深化させている

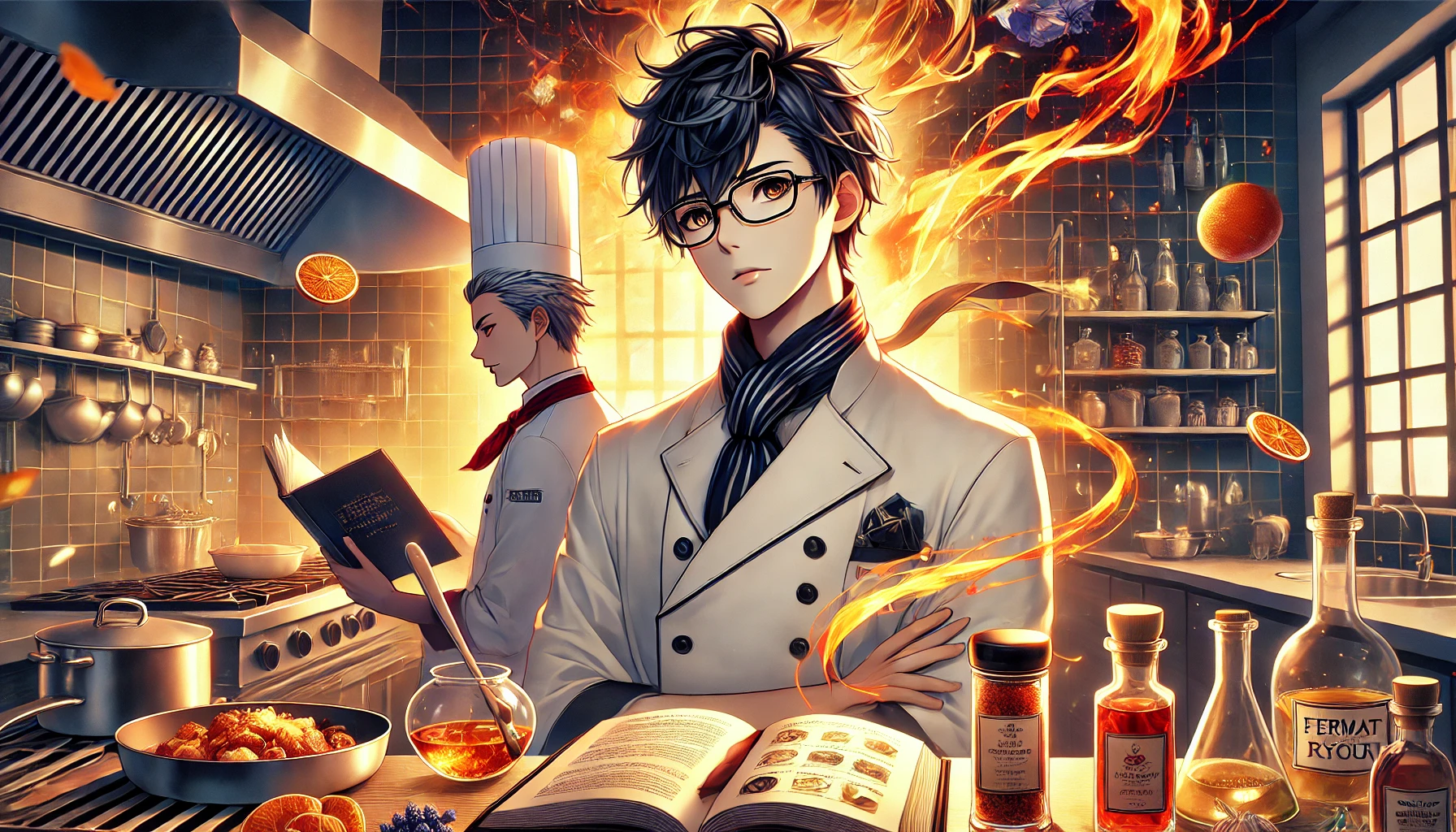


コメント